夏空に浮かぶ月 2025、その12
2025年6月21日の夏至が過ぎて、8月7日が立秋です。
このページでは、旧暦(陰暦)の夏の第12週、2025年7月18日から7月25日まで、
下弦の月の次の日から新月までの月の表情を紹介します。
〜〜〜
再掲しますが、
7月17日は、正午月齢 21.7でした。
旧暦六月二十三日です。
月の出は午後10時47分で、南中時刻は18日午前5時27分、月の入りはお昼の午後0時18分でした。
18日午前9時38分に下弦の月になります。
18日未明にはくっきりとした表情が見えました。
明け側には、午前6時前後にわずかだけ雲の間から見えましたが、
午前6時半以降は、無情にもお昼まで西空が雲で覆われ、
下弦の月の時刻の表情を写すことができず、
この時期特有の、沈む前に弦が横に見える画像は得られませんでした。
二十三日の月の限られた画像です。

左;18日未明の午前2時10分頃、中;午前5時57分頃、右;午前6時19分頃
南中時刻は18日南中時刻は18日午前5時27分でした。
中の画像は、南中時刻から30分後の画像でしたが、夏の下弦の月の特徴が見られます。
18日午前9時38分に下弦の月になり、その3時間後に沈みました。
〜〜〜〜〜
7月18日は、正午月齢 22.7でした。
旧暦 六月二十四日でした。
月の出は午後11時18分、南中時刻は19日の午前6時18分、月の入りはお昼の午後1時29分でした。
午前6時半を過ぎた頃から青空が見え始めました。

左;19日午前2時48分頃、中;午前6時38分頃、右;午前9時33分頃
南中時刻は19日の午前6時18分でした。
中の図は南中時刻を20分後です。
午前10時以降は西空に薄雲が広がり、撮影できませんでした。
東西の軌道から2日後で、真西より14度北側の軌道ですが、
夏の下弦の月の特徴が引き継がれています。
〜〜〜
7月19日は、正午月齢 23.7でした。
旧暦 六月二十五日でした。
月の出は午後11時55分、5分で20日に日が変わります。
7月20日は、正午月齢 24.7でした。
旧暦 六月二十六日でした。
南中時刻は午前7時14分、月の入りは午後2時42分でした。

左;20日午前1時09分頃、中;午前7時28分頃、右;午前11時13分頃
南中時刻は20日午前7時14分でした。
雲が少なく、午後2時半過ぎまで見えました。

20日午後1時46分頃の団地の西空です。
午前11時13分の画像に対して左側に少し逆転して見えました。
本日の日の出、月の出の方角はほぼ同じでしたが、
その後、月の軌道が太陽の軌道よりも北側になりました。
次の月の出は21日の未明になります。
〜〜〜
7月21日は、正午月齢 25.7 でした。
旧暦 六月二十七日でした。
月の出は未明の午前0時38分、南中時刻は午前8時13分、月の入りは午後3時55分でした。
南中時撮影を身構えていましたが、大きな雲集団が流れてきたので、
10分前に撮影しました。
南中時にはお月様は隠れました。

左;21日午前3時52分頃、中;午前6時11分頃、右;午前8時03分頃
南中時刻は午前8時13分でした。
午前4時から午前6時頃までは、見かけの回転がほとんど見られません。
軌道が北端に近付き天心近くになると、このように見えます。
南中時以前は、雲の集団が西から東に流れていてお月様を観察する時間帯に制約がありました。
しかし、幸運にも南中時以降は雲が晴れて、細い月にもかかわらず観察できました。
南中時以降の姿です。

左;午前8時03分頃、中;午前9時25分頃、右;午前10時23分頃
その後も、約1時間毎に撮影を続けました。

左;午前10時23分頃、右;午前11時27分頃
左;午後0時29分頃、右;午後1時37分頃
10時台と11時台とはほぼ同じで、この日撮影した中で、最も水平に近く見えました。
午後0時台以降は、もっと水平近くになるかと思いましたが、光の方向が逆になり始めました。
午後1時台の画像では、明らかに反時計方向に回転しています。
午後2時以降は、画像が薄くて、AFが機能しなくなりました。
マニュアルフォーカスで、とりあえず写し続けました。
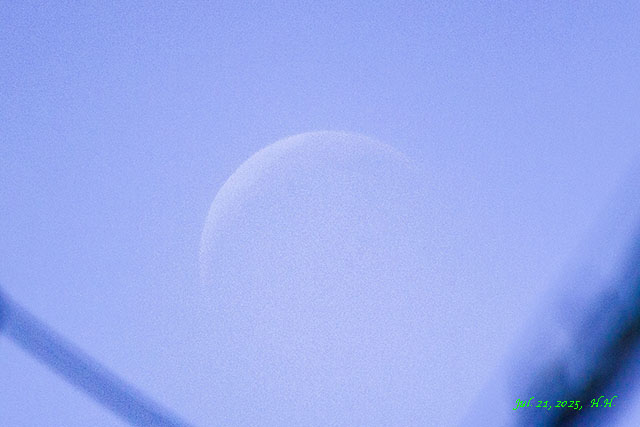
午後2時40分頃のMFでの画像です。
明らかに反時計方向に回転して見えます。
イメージ確認のために、望遠モードから画角を広げて写しました。

午後2時40分頃のMFでの志都呂団地の真西より少し北側の画像です。
電線が作る中央部の三角形の中に微かに写っています。
太陽が夏至を過ぎて、太陽自身の北端の軌道から南側に移動しつつあります。
一方、お月様は、昨日の軌道からさらに北側に移動して23日の北端の軌道を目指しています。
そこで、「keisanサイト」さんによる『月の出月の入り(日本地名選択)』によると、
本日の浜松の太陽の沈む方角は、真西より約27度北側で、
お月さまの沈む方角は真西より約34度北側となり、
お月様より7度ほど南側に移動して、お月様は南側(左側)から照らされるため、
見かけの回転が逆回転に見えることが納得できました。
さて、庭では席が鳴いています。

午後4時頃の庭のカエデに見られた6匹の鳴き終えて休息中のセミたち
〜〜〜
7月22日は、正午月齢 26.7 でした。
旧暦 六月二十八日でした。
月の出は未明の午前1時31分、南中時刻は午前9時16分、月の入りは午後5時03分でした。
次は、月の出から1時間後とさらに2時間後のの表情です。
明け方には金星が並んで見えました。

左;午前3時05分頃、右;午前5時10分頃
わずかですが、見かけ上、反時計方向の回転が見られます。
その後、右側に回転しますが、その過程の姿は観察できませんでした。
南中時直前は、大きな雲の集団が西から東に移動する合間を写しました。

左;午前9時01分頃、右;午前9時44分頃
左;午前10時26分頃、右;午前11時15分頃
南中時刻は午前9時16分でした。

左;午前11時15分頃、右;お昼の午後0時06分頃
右図撮影の頃には、AFが効かなくなりました。
その後は薄雲で西空が白っぽくなり、凝視して眺めましたが、探せなくなりました。
7月22日の浜松でのデータは、
月の出の方角が日の出の方角より約9度北側でした。
同様に、月の入りの方角が日の入りの方角より約10度北側でした。
南中時の高度は83.5度で、月が太陽より約8度天心(北側)側でした。
明後日に新月、明日に北端の軌道になりますが、
今日は、天心近くを眺めながら撮影しました。
〜〜〜
7月23日は、正午月齢 27.7 でした。
旧暦 六月二十九日でした。
月の出は未明の2時33分、南中時刻は午前10時20分、月の入りは午後6時02分でした。
今日のお月さまの軌道は北端の軌道です。

午前3時54分頃の二十九日
明け方には雲が広がり空が白くなり、見えなくなりました。
〜〜〜
7月24日は、正午月齢 28.7 でした。
旧暦 六月三十日でした。
月の出は未明の午前3時42分、南中時刻は午前11時21分、月の入りは午後6時52分でした。
超細い月は明るくなるとすぐに見えなくなるので、薬蔵坂に来ましたが、
全体に薄雲が広がり、富士山は見えましたが、お月様は見えませんでした。
なお、 東の空高く金星は輝いて見えました。

午前4時41分頃の富士山

午前4時42分頃の富士山の風景
お月様が見えれば、鉄塔の右上でした。
〜〜〜
7月25日は、正午月齢 0.3 でした。
旧暦 閏六月一日でした。
午前4時11分に新月になり、約40分後月に出を迎えます。
月の出は午前4時53分、南中時刻はお昼の午後0時17分、月の入りは午後7時32分でした。
月の出の方角;61.5度(東より28.5度北側)、日の出の方角;65.0度(東より25度北側)
月の入り方角;295.1度(西より25.1度北側)、日の入り方角;294.6度(西より24.6度北側)
なお、南中時の高度は、新月は 77度、太陽は 74.9度でした。
〜〜〜
太陽は月とほぼ同時に出て、30分ほど早く沈みました。、
今日の月は太陽に対し、3.5度北側から出て、0.5度北側に沈みました。
明日の月は、太陽より南側に見えることになります。
〜〜〜
夏至からほぼ1ヶ月が経過しました。
夏至を挟む1ヶ月前後の期間における月の見え方について、まとめてみます。
夏至は北半球において太陽の南中高度が最も高くなり、日照時間が最も長くなる時期です。
数値データは「keisanサイト」さんによる『月の出月の入り)』を参照しました。
1. 満月:南の空低くに見える 夏至の頃の満月は、太陽が北寄りの高い軌道を通るのに対し、 南中時の高度の例(浜松): 2. 新月:天頂近くを通るが、見えない 新月は、月が太陽に最も近い位置にあるため、太陽の光に隠れて見ることができません。 南中時の高度の例(浜松): なお、新月前後には、三十日月や二日月の観察ができます。 〜〜〜 東西の軌道を通る半月は、上弦の月と下弦の月でそれぞれ特徴的な見え方をします。 3.上弦の月:南中時に弦が左側(反時計方向)に傾く 上弦の月は、日没後に南の空に見え始め、真夜中頃に沈みます。 南中時の高度の例(浜松): 4.下弦の月:南中時に弦が右側(時計方向)に傾く 下弦の月は、真夜中頃に東の空から昇り始め、日の出の頃に南中します。 〜〜〜 ご参考;太陽の南中時の高度の例(浜松) |
ところで、夏至と冬至の太陽の軌道の南北幅が一定であるのに対して、
月の軌道の南北幅は、19年ほどの周期で変動し、昨年今年は最大幅でした。
白道と黄道とが5度ほど傾いているからです。
特に、昨年と今年の月の軌道の南北幅は最大幅となる時期にあって、
その結果、夏の新月が夏至の太陽より5度ほど北側から出たことになります。
〜〜〜〜〜
月の出時刻は、
下弦の月の頃は深夜から未明でしたが、新月の頃には明け方になりました。
月の入り時刻は、下弦の月の頃はお昼頃でしたが、新月の頃には夕方になりました。
一方、月の軌道は、
6月25日に北端の軌道になった後南下して、7月9日に南端の軌道になり、
その後北上して7月23日に北端の軌道になり、南下を開始しました。
今週は、明け方の東の空の細めの月の月の出の観察がメインでしたが、
来週は、太陽がお月さまに先行して昇るので午前中は見えにくく、
日没後の西空の夕月の月の入りを眺めることになります。
〜〜〜〜〜
次回は、新月の次の日から上弦の月までです。