「夏の月」を歌う和歌、その2
参考書
参考書01;岩波書店 日本古典文学大系 「萬葉集1〜4」
参考書02;新潮社 日本古典集成「萬葉集1〜5」
参考書03;角川ソフィア文庫、高田祐彦訳注 新版「古今和歌集」
参考書04;角川ソフィア文庫、久保田淳訳注 「新古今和歌集 上・下」
参考書05;岩波文庫 久保田淳・吉野朋美 校注 「西行全歌集」
参考書06;明治書院 和歌文学体系「山家集/聞書集/残集」
久保田淳監修、西澤美仁、宇津木言行、久保田淳 共著

佐鳴湖の月の出
この全3ページでは、萬葉集、古今集、新古今集、山家集から「夏の月」を歌う和歌を集めてみました。
この第2ページは、新古今和歌集からの「夏の月」の和歌を集めました。
| ページ | 「夏の月」を歌う和歌の拾集 |
| P1 | 萬葉集より9首、古今、後撰、金葉より各1首、千載集から7種、計 19首 |
| P2 | 新古今和歌集より 18首 |
| P3 | 西行の山家集より 11首、聞書集、残集から各1首、計 13首 |
-----------
「夏の月」を歌う和歌、その2
新古今和歌集から18首
2-1.新古今和歌集からの「夏の月」の歌 8首(参考書 04 より引用)
新古今和歌集
180 卯の花のむらむら咲ける垣根をば雲間の月の影かとぞ見る 白河院
186 花散りし庭の木の葉も茂りあひて天照る月の影ぞまれなる 曾禰好忠
193 五月山卯の花月夜ほととぎす聞けどもあかずまた鳴かむかも 知らず
200 卯の花の垣根ならねどほととぎす月の桂の蔭に鳴くなり 前中納言匡房
209 有明のつれなく見えし月は出でぬ山ほととぎす待つ夜ながらに 摂政太政大臣
210 わが心いかにせよとてほととぎす雲間の月の影になくらむ 俊成
211 ほととぎす鳴きて入るさの山の端は月ゆゑよりも恨めしきかな 前太政大臣
212 有明の月は待たぬに出でぬれどなほ山深きほととぎすかな 権中納言親宗
以下は、参考書04 の大意をそのまま手を入れずに示します。
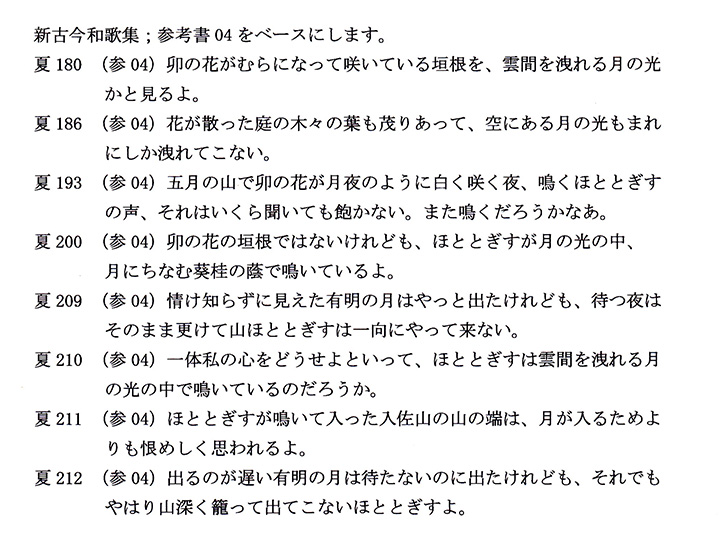
180番の結題は「卯花月の如し」で、この先行歌として、その1に記載した2つの歌
金葉・夏・江侍従の歌、千載・夏・藤原顕輔の歌が示されていました。
186番の歌の反対に、昨年記載した晩秋の歌の中には、木の葉が落ちて
月が見えるようになる喜びを歌うものが見られます。
193番の歌の原歌は、萬葉集の1953番の歌と記述されています。
211番の歌は、その1に記載した千載・夏・藤原宗家の歌を念頭に置いた歌と記載されています。

庭のカエデの木々の間から漏れ来る月の光
-----------
2-2.新古今和歌集からの「夏の月」の歌 10首(参考書 04 より引用)
229 真菰刈る淀の沢水深けれど底まで月の影は澄みけり 前中納言匡房
233 さみだれの雲の絶え間をながめつつ窓より西に月を待つかな 荒木田氏良
235 さみだれの頃の月はつれなきみ山よりひとりも出づるほととぎすかな 藤原定家朝臣
237 さみだれの雲間の月の晴れゆくをしばし待ちけるほととぎすかな 二条院讃岐
1982 さみだれの空だに澄める月影に涙の雨は晴るる間もなし 赤染衛門
249 庭の面は月もらぬまでなりにけり梢に夏の蔭茂りつつ 白河院御歌
258 むすぶ手に影乱れゆく山の井のあかでも月のかたぶきにける 前大僧正慈円
259 清見潟月はつれなき天の戸を待たでもしらむ波の上かな 権大納言通光
260 重ねても涼しかりけり夏衣うすき袂に宿る月影 摂政太政大臣
267 庭の面はまだかわかぬに夕立の空さりげなく澄める月かな 従三位頼政
258番の歌以外は、参考書04 の大意をそのまま手を入れずに示します。
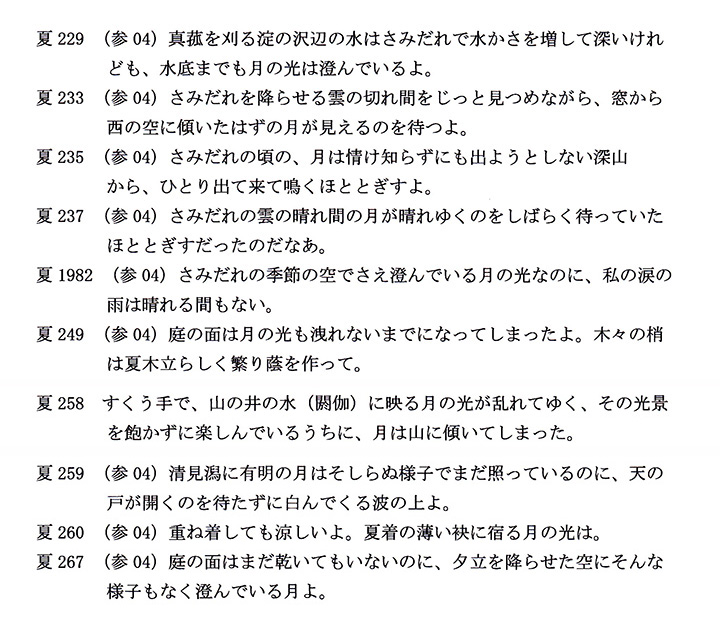
249番の歌も186番の歌に近く、木が茂って月が見にくくなったことを嘆いています。
259番の歌は、その1に記載した千載集の216番の歌を連想させます。
267番の歌は、その1に記載した千載集の217番の歌同様、夕立ちの後の澄んだ月が歌われています。

木の間から洩れる夏の月
-----------
ところで、258番の歌には、興味関心が深く、追記したいと思います。
前大僧正慈円のこの歌の本歌は、次に示す紀貫之の歌です。
古今 404 むすぶ手のしづくににごる山の井のあかでも人に別れぬるかな 紀貫之
同時に、思い浮かぶ歌は、
拾遺集 1322 手に結ぶ水にやどれる月影の あるかなきかの世にこそありけれ 紀貫之
この歌は、貫之辞世の歌として知られ、個人的にも印象深い歌です。
しかも、今回、「夏の月」その3においても、西行の類似の歌2首があります。
山家集 243 掬びあぐる泉に澄める月影は手にも取とられぬ鏡なりけり 西行
山家集 244 掬ぶ手に涼しき影を慕ふかな清水に宿る夏の夜の月 西行
ここで、私は手に掬った水に月がどのように映るのか知りたくなりました。

左は、5月4日午前3時頃の月です。右は、地面に置いた柄杓の水を介してその月を眺めたものです。
柄杓を手に持って月を見る場合、見ることはできますが月の虚像が安定しません。
手を動かさないよう努力しても、風も邪魔することがわかりました。
さらに、手ですくった水に月を映して見ることはさらに至難の技でした。
水が手からこぼれますので、何回も水をいっぱいに掬い直すことが求められました。
また、明け方に東の空が明るくなると、西空に浮かぶ月を柄杓の水に映るのを目で確かめるのはさらに困難になりました。
以上の実験から、歌から情景を想像することは容易ですが、
実際に手に掬った水に月を見ることは大変難しいことがわかりました。
そこで、前大僧正慈円の258番の歌を現代語にするとき、
手に掬った水に映る月ではなく、山の井に映る月と表現しました。
山の井の水面でさえ、掬う手で揺らされ、散り落ちる水で揺らされ、
風が吹いても水面は不安定で、月の映りを見ることは難しくなります。
だからこそ、水を飲むにも、月の映りを確認するということは、
当時の楽しみ、一種の遊びだったのかも知れません。
一方、拾遺集 1322番の「貫之の辞世の歌」は、手に結ぶ水にやどれる月影を通して、
味わい深くしみじみと再認識することができました。
-----------
次は、このシリーズ最後の第3ページとして、西行の山家集、聞書集、残集に見る「夏の月」の歌を拾集します。