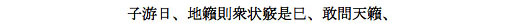大濱 晧(皓)
荘子の哲学
勁草書房
1966年3月30日 |
千種万別のうろや穴に風が吹きつけると、千種万別の音色がおこる。そしてそれらは自然にやむ。それぞれ自然にそうなるのである。さまざまな音色をおこすのは誰なのだ。己よりせしむるもの、すなわち自然である。そしてそれこそ天籟にほかならない。真の主宰者があるようであるが、また真宰のはたらきがあることは信実であるが、その形体を見ることはできない。これが天籟である。・・・身体の各器官が秩序正しく動いている以上、そうさせるものがなければならない。人間が真君の真君たる本質をとらえることができなくても、真君たる絶対者の実在には何の変化もない。これが天籟である。三つの比喩により
木でも風でもなく、人間でも社会でもなく、心でも体でもなく、これらの相違を主宰しとういつするものは唯一のもの、絶対者、天籟であつた。それは生命の躍動する、有機的な、自然の、統一原理であった。(p343-p347)
|
森美樹三郎
世界の名著
「老子荘子」
中央公論社
1968年7月10日
荘子
中公クラシックス
2001年9月25日
|
天籟の風が、無数の洞穴にそれぞれの音をたてさせるように、人間の感情の生起の背後にも、何ものかの存在が予想される。それは宇宙の主宰者とよんでもよいだろう。だが、その主宰者は形のないものであり、人間の目ではとらえられないものである。しかし、目で確かめられないということは、そのものが存在しないという証拠にはならない。たとえば人間の身体の諸器官は、それぞれ独立の機能をもつにもかかわらず、真宰とでもいうべきものによって統一されている。その真宰は目に見えないが、しかもそれが存在することは厳然とした事実である。とするならば、人間を喜び悲しませる主宰者の存在も、やはり疑いえない事実であろう。
それでは、その宇宙の主宰者とは何か。・・・・・その主宰者が、天であり、道であり、自然であり、運命であり、絶対的な一者であることは、他の諸篇とあいまって、やがて解明される。
|
森美樹三郎
老子・荘子
講談社学術文庫
1994年12月10日
|
だが、荘子はいつの場合でも、この運命の主宰者を姿あるものとして描くことがない。描かないのではなくて、描けないのである。なぜなら、それは世の常の意味での存在ではないからである。
実は荘子のいう造物者、造化者とは、自然の別名であり、無限者の仮りの名である。人間がこの地上に生まれたのは、造物主といった他者の力によるのではなくて、自然・必然の運命によるものである。さきに自然を定義して「他者の力によらないで、それ自身の内にある働きによってそうなること」といった。もし、われわれが主宰者や神といった他者から運命をあたえられるとすれば、われわれは他然となり、自然でなくなってしまう。
自然は人為を排除するばかりではなく、神をも排除する。徹底した自然主義者、運命論者である荘子は、同時に無神論者でもあった。(p88-p89)
|
金谷治
岩波文庫
1975年5月16日 |
地の簫も人の簫も、そもそも吹き方はさまざまで同じではないが、それらは、みなそれぞれに自分で音を出しているのだ。すべてそれ自身で音が選ばれている。音を出させる者はいったい何者であろう(そんな者はありはしない)。
・・・それでいて、何がそのようなさまざまな状態を起こさせるのかは分からない。真宰:真の主宰者がいるようでもあるが、その形跡は得られない。作用(はたらき)の結果は確かであるが、そうさせたものの形は見えない。実質はあるが姿形はないのである。
|
福永光司
朝日新聞社
1978年9月5日 |
天籟とは人籟・地籟のほかさらに天籟とよばれる別の籟きがあるのではなくて、地籟を地籟として聞き、人籟を人籟として聞くことが、そのまま天籟だというのである。
世俗の立場では、すべての響きは響きを発せしめる「何か」もしくは「誰か」がその背後にあって、すべての響きが響きになると考えられる。あらゆる現象の奥には、現象を現象として成り立たしめる一者(神)が存在するというのが世俗の立場である。そこでは、・・・・・。しかし、彼は万籟の響きは、みな自己自身の原理によって響きとなるのであって、それを背後において響きとならしめる何物も存在しないという。天籟とは、この自己自身の原理によって響きとなる万籟を、そのまま万籟として聞くことにほかならない。・・・・・。
人間の精神と肉体の営みの背後には(においても)、その営みを支配する絶対者が存在するかのごとくであるが、しかし、その絶対者は、「情(まこと)ありて形(かたち)なき」はたらきそのもの、変化それ自体であり、その真宰とは、自然、天ということにほかならないのである。人はただこの「自然」を自然として受け取る時にのみ、真の自己となることができる。自然の世界の万籟をそのまま天籟として聞くように、人間の生の営みの一切を、ただ天、自然として受け取る時に、人はその人間的なる一切のものから超越することができるのである。
|
中島隆蔵
荘子
集英社
1984年12月25日 |
地籟、人籟とは別に天籟と称すべきものが存在するわけではない。これら一切の相集るところ、これがほかならぬ天籟である。相集って天籟となる、その一つ一つは、それぞれに自然必然のさだめとして、そこにそう在りえており、それ以外の他の何物かの働きによって、そう在りえているのではない。・・・天も地も、物も我も、すべてひとしなみに在るがままにそう在ること、それらを生み出し、それらを使役する何物もないままに、すべてがかく在ること、これこそが天籟である。
|
諸橋轍次
荘子物語
講談社学術文庫
1988年10月10日 |
風に聞いてみると、この音は私が鳴らしているのだと言う。穴に聞いてみると、これは私が鳴らしているのだと言う。けれども、もう一歩考えてみると、いったい何がこの風を起こし、そうして何がこの木の穴にぶつけているのであろうか。そこをひとつ考えてみると、どうもほんとうの支配者(真宰)があるような気持がする。そこを考えておくのがすなわち天籟を聞くことである。
|
岸陽子
荘子
徳間書店
1996年8月31日 |
地籟にせよ、天籟にせよ、鳴るものは千差万別だが、それぞれおのずからなる音を生じ、おのれの音色に鳴り響く。いったい何者がそうさせているのか?
万物があるがままに調和しているすがた、それが天籟にほかならない。天籟を聞くとは、いっさいの思惟を去り、自他の区別を忘れて虚心(うつろ)になりきった状態を指す。その時、人ははじめてこの限りない調和の世界に入ることができるというのである。人間心理の諸相はいったい何から生ずるのであろうか。真宰の存在を前提としなければ論理が通らぬ。しかし、その存在を明示することはできないのである。・・・人体についても、真君の存在を考えたいが、われわれがそれを知り得ようと知り得まいと人体が一つの統一をなしている事実には、なんの影響もないのだ。
|
蜂谷邦夫
荘子=超俗の境へ
講談社選書メチエ
2002年10月10日
蜂谷邦夫
老子・荘子をよむ
NHK出版
2010年10月1日
|
風の吹き方はさまざまであるが、もろもろの穴に当たればもろもろの音を出し、その音はすべてそれぞれの穴が自然に出しているのだ。その音を出させようとしているのは、いったい、誰なのであろうか(そんなものはいない)、と。
天地自然の世界には風を吹かせて木々に音を出させようとしている者(主宰者)などはいない。・・・そして、木の穴に風が当たって出る音は、風と穴それ自体が発する自ずからのものだ、と認識するとき、その音こそ天籟にほかならない。
・・・風に吹かれる木々が万籟の声を発するように、我々の心もまた瞬時もざわめきをやめない。・・・我々のこころのざわめきもまた自然の働きとして認識されてくる。心の働きは意識の関わらないところで勝手に動く。心に真宰があるようであるが、その痕跡は得られない。情況はあっても形はないのだ。身体の各部分の働きについても、その主君つまり真宰はわからない。
|
| |
|