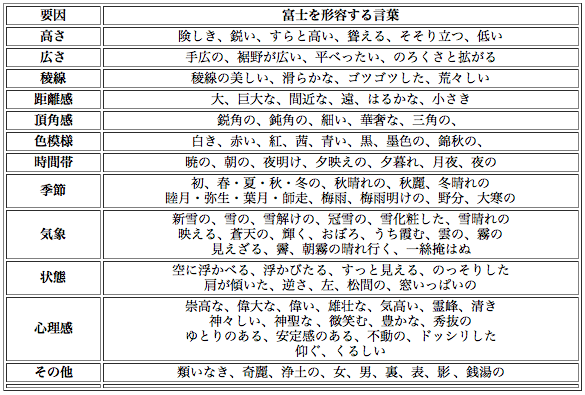仮題 |
太宰の富士への表現の一部 |
出だしの
一部 |
たいていの絵の富士は、鋭角である。いただきが、細く、高く、華奢である。・・・ 実際の富士は、鈍角も鈍角、のろくさと拡がり、東西、百二十四度、南北は百十七度、決して、秀抜の、すらと高い山ではない。・・・低い。裾のひろがっている割に、低い。あれくらいの裾を持っている山ならば、少くとも、もう一・五倍、高くなければいけない。
|
十国峠 |
十国峠から見た富士だけは、高かった。あれは、よかった。・・・・・ 私が、あらかじめ印(しるし)をつけて置いたところより、その倍も高いところに、青い頂きが、すっと見えた。
|
東京から
見た富士 |
東京の、アパートの窓から見る富士は、くるしい。
小さい、真白い三角が、地平線にちょこんと出ていて、それが富士だ。クリスマスの飾り菓子である。しかも左のほうに、肩が傾いて心細く、船尾のほうからだんだん沈没しかけてゆく軍艦の姿に似ている。
|
天下茶屋
から |
あまりに、おあつらえむきの富士である。まんなかに富士があって、その下に河口湖が白く寒々とひろがり、近景の山々がその両袖にひっそり蹲(うずくま)って湖を抱きかかえるようにしている。私は、ひとめ見て、狼狽し、顔を赤らめた。これは、まるで、風呂屋のペンキ画だ。芝居の書割だ。どうにも註文どおりの景色で、私は、恥ずかしくてならなかった。
|
三ツ峠
頂上から |
急に濃い霧が吹き流れて来て、頂上のパノラマ台という、断崖(だんがい)の縁(へり)に立ってみても、いっこうに眺望がきかない。何も見えない。
ほんとうに生憎(あいにく)の霧で、もう少し経ったら霧もはれると思いますが、富士は、ほんのすぐそこに、くっきり見えます、こんなに大きく、こんなにはっきり、このとおりに見えます、と懸命に註釈するのである。 私たちは、番茶をすすりながら、その富士を眺めて、笑った。いい富士を見た。霧の深いのを、残念にも思わなかった。
|
天下茶屋の
二階廊下で |
「どうも俗だねえ。お富士さん、という感じじゃないか。」
「見ているほうで、かえって、てれるね。」
などと生意気なこと言って、煙草をふかし、そのうちに、友人は、ふと、
「おや、あの僧形(そうぎょう)のものは、なんだね?」と顎でしゃくった。
墨染の破れたころもを身にまとい、長い杖を引きずり、富士を振り仰ぎ振り仰ぎ、峠をのぼって来る五十歳くらいの小男がある。
「富士見西行、といったところだね。かたちが、できてる。」私は、その僧をなつかしく思った。「いずれ、名のある聖僧かも知れないね。」
「ばか言うなよ、乞食(こじき)だよ。」友人は、冷淡だった。
|
天下茶屋の
部屋から |
私は、部屋の硝子戸越しに、富士を見ていた。富士は、のっそり黙って立っていた。偉いなあ、と思った。「いいねえ。富士は、やっぱり、いいとこあるねえ。よくやってるなあ。」富士には、かなわないと思った。念々と動く自分の愛憎が恥ずかしく、富士は、やっぱり偉い、と思った。よくやってる、と思った。
|
吉田の
町で |
その夜の富士がよかった。
おそろしく、明るい月夜だった。富士が、よかった。月光を受けて、青く透きとおるようで、私は、狐に化かされているような気がした。富士が、したたるように青いのだ。燐が燃えているような感じだった。鬼火。狐火。ほたる。すすき。葛(くず)の葉。
そっと、振りむくと、富士がある。青く燃えて空に浮んでいる。
|
天下茶屋
から |
富士に雪が降ったのだ。山頂が、まっしろに、光りかがやいていた。御坂の富士も、ばかにできないぞと思った。やはり、富士は、雪が降らなければ、だめなものだ。
|
帰りの
バスにて |
私もまた、富士なんか、あんな俗な山、見度くもないという、高尚な虚無の心を、その老婆に見せてやりたく思って、三七七八米の富士の山と、立派に相対峙し、みじんもゆるがず、なんと言うのか、金剛力草とでも言いたいくらい、けなげにすっくと立っていたあの月見草は、よかった。富士には、月見草がよく似合う。
|
天下茶屋の
部屋から |
部屋のカーテンをそっとあけて硝子窓越しに富士を見る。月の在る夜は富士が青白く、水の精みたいな姿で立っている。
|
単一表現の
美しさ |
眼前の富士の姿も、別な意味をもって目にうつる。この姿は、この表現は、結局、私の考えている「単一表現」の美しさなのかも知れない、この富士の、あまりにも棒状の素朴には閉口して居るところもあり、これがいいなら、ほていさまの置物だっていい筈だ、ほていさまの置物は、どうにも我慢できない、あんなもの、とても、いい表現とは思えない、この富士の姿も、やはりどこか間違っている、これは違う、と再び思いまどうのである。
|
天下茶屋
にて |
寒空のなか、のっそり突っ立っている富士山、そのときの富士はまるで、どてら姿に、ふところ手して傲然とかまえている大親分のようにさえ見えたのである。
|
天下茶屋
にて |
その全容の三分の二ほど、雪をかぶった富士の姿を眺め、・・・・・、レンズをのぞいた。まんなかに大きい富士、その下に小さい、罌粟(けし)の花ふたつ。
|
甲府の宿
から |
そのあくる朝、安宿の廊下の汚い欄干によりかかり、富士を見ると、甲府の富士は、山々のうしろから、三分の一ほど顔を出している。酸漿(ほおずき)に似ていた。
|